国民年金の給付の種類
国民年金から支給される「基礎年金」は、次の種類の給付があります。
- 老齢基礎年金
- 障害基礎年金
- 遺族基礎年金
また、第1号被保険者の独自給付としては、次の種類の給付があります。
- 付加年金
- 寡婦年金
- 死亡一時金
請求に必要な書類については、事前にお問い合わせください。
老齢基礎年金
受給資格
保険料を納付した期間(免除期間も含みます)が原則10年以上ある方に、65歳から支給されます。
金額(令和7年度)
受給開始までに納付した月数によって決定されます。
20歳から60歳になるまでの40年間の保険料をすべて納めた方は、満額の年額 831,700円が支給されます。
※昭和31年4月1日以前に生まれた方の満額は、年額829,300円になります。
源泉徴収票の送付について
日本年金機構から源泉徴収票が毎年1月中旬頃に送付されます。源泉徴収票は1年間の年金支払い総額などを記載しており、確定申告の際にご利用いただけます。
紛失・破損した場合の再発行については、豊中年金事務所(電話06-6848-6831)にお問い合わせください。
詳しくは日本年金機構ホームページを参照してください。
障害基礎年金
受給資格
加入者(被保険者)が病気やけがで障害者になった場合に、一定の条件を満たしている方に支給されます。
注意事項:20歳前に初診日がある方の障害基礎年金については、年金の加入を要件としていないことから、年金の支給に関して制限や調整があります。本人に一定以上の所得がある場合等は、支給の一部または全部が支給停止となります。
金額(令和7年度)
•1級障害:1,039,625円(年額)
※昭和31年4月1日以前に生まれた方:1,036,625円(年額)
•2級障害:831,700円(年額)
※昭和31年4月1日以前に生まれた方:829,300円(年額)
注意事項:障害年金における障害等級は、障害者手帳等とは認定基準が異なります。
また、受給権者によって生計を維持されている子がいる場合は、次の額が加算されます。
(「子」とは、18歳に達する日以降の最初の年度末(3月31日)までの間にある未婚の子または、20歳未満で国民年金の障害等級1級または2級に該当する未婚の子をいいます。)
1人目・2人目:1人につき 239,300円(年額)
3人目以降:1人につき 79,800円(年額)
遺族基礎年金
受給資格
一定の条件を満たす方が死亡した場合に、その方に生計を維持されていた、「子」のある配偶者または「子」に支給されます。
(「子」とは、18歳に達する日以降の最初の年度末(3月31日)までの間にある未婚の子または、20歳未満で国民年金の障害等級1級または2級に該当する未婚の子をいいます。)
金額(令和7年度)
子のある配偶者が受け取る場合
831,700円(年額)+子の加算額
※昭和31年4月1日以前に生まれた方 829,300円(年額)+子の加算額
子が受け取る場合(次の金額を子の数で割った額が、1人あたりの金額です。)
831,700円(年額)+(2人目以降の子の加算額)
子の加算額
1人目・2人目:1人につき 239,300円(年額)
3人目以降:1人につき 79,800円(年額)
第1号被保険者の独自給付 付加年金
第1号被保険者が定額の保険料と合わせて付加保険料(月額400円)を納付した期間について、老齢基礎年金に上乗せして支給されます。
ただし、国民年金基金に加入している方は、付加保険料を納付することはできません。
金額
200円×付加保険料納付月数(年額)
注意事項:繰上げ・繰下げ請求をした場合は、支給率が変わります。
寡婦年金
第1号被保険者としての保険料納付済期間と免除期間をあわせて10年以上ある夫が死亡したとき、次の条件をすべて満たす妻に60歳から65歳になるまでの間支給されます。
- 婚姻関係が10年以上続いている(事実上の婚姻関係を含む)
- 夫が障害基礎年金、老齢基礎年金を受け取ったことがことがない(※)
- 夫によって生計を維持されていた
- (※)夫の死亡日が令和3年3月31日以前のときは、夫が障害基礎年金の受給権がない場合、夫が老齢基礎年金を受け取ったことがない場合に支給されます
金額
夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3です。
注意事項:本人(妻)が繰上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合は、支給されません。
死亡一時金
第1号被保険者として、保険料納付済期間が3年以上ある方が、老齢基礎年金または障害基礎年金を受けずに死亡したとき、生計を同じくしていた遺族((1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹の中の優先順位の高い方)に支給されます。
ただし、遺族基礎年金を受け取ることができる方がいる場合には支給されません。
死亡日の翌日から2年を経過すると、死亡一時金を受ける権利は消滅します。
注意事項:同一人の死亡により、死亡一時金と寡婦年金が受けられる場合は、受給権者の選択によりどちらかひとつが支給されます。
金額
保険料納付済期間に応じて、12万円から32万円
付加保険料を納めた月数が36月以上ある場合は、8,500円が加算されます。
この記事に関するお問い合わせ先
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:
(国民健康保険)072-754-6253
(国民年金)072-754-6395
福祉部国保・年金課へのご意見・お問い合わせ





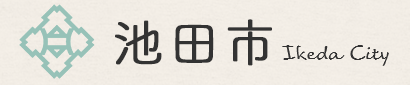

更新日:2025年04月01日