福祉援助
生活保護
生活保護制度とは
生活保護制度は、病気や高齢のため働くことができなくなったり、思いがけない事故や障がい、世帯の働き手を失ったりすること等により生活に困っている人に、憲法第25条の理念に基づき国が最低限度の生活を保障しながら、一日も早く、自分たちの力、または他の方法で自立した生活ができるように援助する制度です。
生活保護の要件等
生活保護は、下記のような保護制度以外に利用できるすべてのものを活用しても生活に困窮する場合、「国が定めた基準に基づき計算される生活費(最低生活費)」と「世帯の収入(年金、各種手当等を含む)」を比較し、「世帯単位」で生活保護の判断を行います(生活保護法第10条)。世帯の収入が最低生活費を下回る場合、生活保護が決定、適用され、その不足分が生活保護費として支給されます(生活保護法第4条)。
○資産の活用が要件 → あなたの世帯の生活必需品以外の資産は、処分あるいは最大限に活用して、生活費に充ててください(例えば、預貯金、有価証券、仮想通貨、各種保険、貴金属類等)。
○能力の活用が条件 → 就労できる方は働いて収入を得てください。
○扶養義務者による扶養が優先 → 親子、兄弟姉妹等、援助ができる身内があれば援助を求めてください。特に中学生以下の子どもとその親(父母)は非常に強い扶養義務関係にあります。
○他の法律による給付等が優先 → 他の法律による給付等を受けることができるときや、貸付金等を利用できるときは、まずその制度を活用してください。
他の法律による給付等の例
□雇用保険法による給付(基本手当、傷病手当等の失業等手当)
□求職者支援法による職業訓練給付金
□公的年金(老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金等)
□児童手当
□児童扶養手当
□特別障がい者手当
□障がい児福祉手当
□自立支援医療制度(医療費を助成する制度)
□介護サービスによる給付
□高額介護サービス費
□高額療養費(限度額適用認定証)
□入院助産
□老人福祉法、障害者総合支援法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法等による福祉サービス
生活保護の種類
生活保護には、次の8種類の扶助があり、必要に応じ、基準の範囲内で支給されます。
○生活扶助:生活に必要な食費や衣類、光熱水費等の費用です。
○住宅扶助:家賃、地代、住宅維持費等の費用です。
○教育扶助:義務教育に必要な教材費、給食費等の費用です。
○介護扶助:介護サービス、福祉用具購入、住宅改修費等の費用です。
○医療扶助:病気やけが等の医療費や通院移送費等の費用です。
○出産扶助:出産に要する費用です。
○生業扶助:高等学校修学時の授業料や教材費等の費用、仕事の技能を身につけるために必要な費用です。
○葬祭扶助:葬儀、死亡診断書料等の費用です。
生活保護の相談・申請時に準備していただきたいもの
□ 預貯金通帳 【銀行(ネット銀行を含む)、郵便局等すべて(家族の方全員対象です)の記帳を済ませてきてください】
(Web通帳や電子マネーをご利用の場合は、面談時に画面上で内容を確認させていただきます。)
□ 保険証書 【生命保険・損害保険等。解約した場合も、わかるものをお持ちください】
□ 賃貸契約書 【公営住宅の場合は今年度の家賃決定通知書】
□ 家賃の領収書 【通い・銀行振込み領収書等】
□ マイナンバーカード【なければ、通知カードかマイナンバーが記載された住民票】
□ 給与明細(最近3ヶ月分) 【就労されている方、また最近退職された方のみ】
□ 親子、兄弟姉妹等、親族の住所・氏名・生年月日・電話番号を書いたメモ
上記の書類がなくても相談・申請は可能ですが、上記の書類があれば、より具体的な相談・申請をすることができますので、できる限りご準備ください。
詳しくは、生活福祉課(電話番号:072-754-6251)までお問い合わせください。
※来所による相談は混み合う場合がありますので、できるかぎり事前に、生活福祉課(電話番号:072-754-6251)まで、ご予約していただくようお願いします。
※原則、予約優先で対応しますのでご協力お願いします。
生活福祉課、電話番号:072-754-6251
災害見舞金・災害弔慰金
災害・事故の被災者に被災程度によって災害見舞金・弔慰金を支給します。
(り災した日または入院加療が3ヶ月を超えた日から6ヶ月以内に申請してください。)
生活福祉課、電話番号:072-754-6251
福祉貸付金等
1年以上市内に在住の低所得者世帯を対象に生活資金、高等学校入学準備貸付金の貸し付けを行っています。無利子ですが、限度額があり、また保証人が必要で、所得制限があります。あわせて、一定の世帯に対し交通遺児奨学資金貸付金の貸し付けも行っています。
生活福祉課、電話番号:072-754-6251
戦没者の遺族などの方へ
戦没者遺族や戦傷病者などの援護についてご相談ください。
高齢・福祉総務課、電話番号:072-754-6250





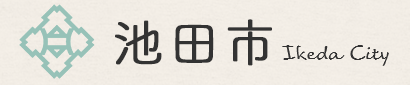

更新日:2024年11月28日