第10回ふくまる夢たまごセミナー
日時 1月20日(金曜日)18時~20時
場所 市庁舎7階 大会議室
内容 授業づくり・指導案づくり
○講義1「ICTを活用した授業づくり」
講師:大賀健司(池田市教育センター 副主幹)
○講義2「『授業づくり』と『指導案づくり』」
講師:河合啓志(学校教育推進課 指導主事)
新しい年(平成29年・2017年)を迎え、29名の塾生が元気に参加してくれました。
今回は10回目のセミナーでした。2月の閉塾式を残し、平成28年度(第6期)の「ふくまる夢たまごセミナー」の講義としては最終となります。
講師は、池田市教育センター副主幹の大賀健司先生と、学校教育推進課指導主事の河合啓志先生にお願いし、それぞれ、「ICTを活用した授業づくり」と「授業づくりと指導案づくり」をテーマにお話していただきました。

大賀先生は、これからの学校教育(授業)にICTの活用が欠かせないことを前提にしつつ、その使い方次第では逆効果になることもあると説き、つまるところ教師の子ども理解や授業力の向上こそが大事であるとお話されました。

河合先生からは、「紙風船」(黒田三郎詩集「もっと高く」より)を題材にした模擬授業を通し、授業づくりの視点、子どもの分かり方を可視化すること等々、子どもも教師も楽しむ授業づくりについて話していただきました。
こうした二人の先生のお話をメモにまとめた塾生の記録を、次に紹介します。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1.講義1「ICTを活用した授業づくり」
・学び・・・発見すること、創り出すこと、課題を解決すること
・ファシリテーター・・・子どもの考えを引き出し、意見をつなげ、発見や解
決に導く
・なぜICTを活用するか意味を考える
→情報量のコントロールが鍵になる。(いかに見せないかが大事)
・実物に勝る教材はない
→実験やフィールドワークの重要性
・子どもにいかに学ばせるか
→考え続けていくところ
2.講義2「授業づくり」と「指導案づくり」
・さまざまな場面から子ども理解ができる
<例>話している時の体の向き
・一時間が終わって、子どもが仲良くなったかどうか
1.見えなかったものが見えるようになるか(=教科内容)
・発見の感動
2.どのように見えるようになったか(=方法)
・相手を意識した話し方をする子どもを育てる
3.自分が子どもだったら受けたい授業であるか(=工夫)
・楽しさの質を上げる
・ステップ型(旅行で言う「ツアー」)とフィールド型(旅行で言う「フ
リープラン」)
☆最終的には、「子どもが楽しいかどうか」
・自分のレベルを把握する
・慌てず、追い求め続ける
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Fさんの「セミナー受講の記録」より転記
講話後は、お二人の講話を受けて、いつものように熱心なグループ討議が行われ、それぞれの代表が、話し合われたことを簡潔にまとめ、報告をしてくれました。




<塾生の感想から>
○ICTの活用として、“使えば授業が良くなるわけではない”という言葉が印象に 残りました。「いかに見せないか」という工夫も新たな視点で、とても参考になりました。
また、授業づくりの視点として、教材研究や発問、指示ばかりに注意がいってしまいがちでしたが、そこに「子どもが楽しいか」という新たな視点が加わりました。自分の良さを活かし、自分しかできない授業をつくってみたいという気持ちになりました。自習時間の使い方もとても参考になりました。
○「ICTを活用した授業づくり」というと、たくさん使用することで子どもの興味をひくイメージが強かった。でも、大賀先生の話を聞くことで、「分かったつもり」に陥らないためにも、情報をコントロールする、板書やノート指導を大切にした上で、適度に興味をひくことの重要性を学んだ。有効なICT教材を選び、ICTを利用する良さを活かせるようになれたらと思う。
「授業づくり」では、子どもが、自ら知りたい、調べたいと思える発問が大切ではないかと思う。その気持ちを持った子どもたちなら、主体的な学びを取り入れた際、有効に時間を使ってくれるのではないかと思った。
○ICTと聞くと、難しいイメージと授業を良くするのだという概念がありました。しかし、ICTで授業を良くするのは、先生の使い方次第であり、なぜICTでなければいけないのかをしっかり考えて授業に取り入れることが大切だと感じさせられました。
授業の導入で子どもをひきつけることが大事だとよく耳にしていたのですが、声を出して活気を出したり、注目させたり、見せない場面を作ったり、紙の配り方を工夫してみたり、いろいろな方法を学ぶことができました。また、楽しさの質を考えて、学期ごとや自分のステージによって授業の楽しさを考えることの大事さを学びました。
フリープランの中で、子どもにどう知識をつかませるのか考え続けて生きたいです。
○私はICTについて間違った理解をしていたことに気づきました。ただ、動画や 写真を見せていれば少しでも興味がひけて良いと思っていました。しかし、これでは何も意味がなく、なぜICTなのかについて考える必要があると感じました。
河合先生のお話では、「発見させる」ことの大切さについて学びました。中学の社会でも、ただ知識を教えるだけではなく、因果関係を考えさせることで「発見させることができる」とのアドバイスをいただいて、これから模擬授業などで、是非、使わせていただこうと思いました。
“自分で欲して獲たものは残る” そのとおりだと感じました。自ら主体的に学んでいけるような授業づくりの基本を学べた気がします。本当にためになるお話でした。





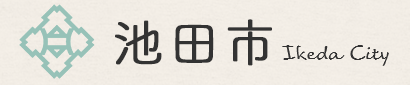

更新日:2021年02月01日