鬼貫の俳句短冊
上嶋鬼貫(うえしま-おにつら)
万治4年(1661)~元文3年(1738)。現兵庫県伊丹市に酒造業油屋(酒銘三文字)当主の三男として生まれる。幼名竹松。通称は利左衛門・藤九郎・与惣兵衛・半蔵。名のりは宗通(むねちか)、後に秀栄(ひでのり)。入道して即翁。晩年は平泉姓を称す。本姓は藤原。別号に自春奄・■々哩<<■は、口へんに羅>>・犬居士・馬楽童・仏兄(さとえ)・槿花翁・金花翁。
8歳のころから俳諧に親しむ。維舟(重頼)・季吟・宗因らの指導を受け、伊丹に来住した維舟門の宗旦に就く。初入集は、16歳の折の維舟撰『武蔵野』か。延宝6年(1678)の『当流籠抜(かごぬけ)』以下、宗旦一門で『俳諧無分別』『西瓜三ッ』や独吟『恵能録』などを編集刊行。随筆風の俳論書『独ごと』は、版を重ねてよく読まれた。自伝の『藤原宗邇伝』、句録『仏兄七久留万』などもある。
25歳の折に大坂に出て学問に励み、また、伊丹資本を背景に経済官僚として、筑後三池藩・大和郡山藩・越前大野藩の京・大坂留守居役などを勤め、伊丹領主近衛家の家来分にもなされた。元禄はじめごろ、「まことの外に俳諧なし」と”大悟”し、その点において、芭蕉と並び称される。大坂に住することが長く、そこで没したが、京にも住み、故郷伊丹の旧友とも深く交わっていた。
鬼貫に関する池田市立歴史民俗資料館収蔵品

短冊の読み
(写真では見えないが上部余白に、「世の中を捨よ捨よとすてさせて跡から拾ふ坊主とも哉」との前書がある。)
鬼つら
「古寺に皮むく椶欄の寒け也」
(C)池田市教育委員会(池田市立歴史民俗資料館)
鬼貫に関する池田市立歴史民俗資料館収蔵品??
憚悟爐文庫目録
(短冊)B俳句
07 鬼貫:古寺に皮むく椶欄の寒け也
(前書 「世の中を捨よ捨よとすてさせて跡から拾ふ坊主とも哉」)
蝸牛廬文庫目録(2)
0165 鬼貫句選:上島鬼貫、明和6、1冊
1187 俳諧文庫素堂鬼貫全集:博文館編 明治30~34、24
1205 俳人鬼貫:宮垣四海編、明治42、1冊
蝸牛廬文庫目録(3)
(書画の部)未装品
91 波々部柳雨:「鬼貫忌三句」、13.0×12.4
(林田良平翁の稿本・写本の部)各種資料2
01 伊丹郷土資料(全1袋25点)
鬼貫弔魂碑建設の趣意書、伊丹播陽会、昭和2、活版、1枚
橋本香坡遺墨展覧会出品目録、伊丹図書館、昭和9、活版、1枚
多田莎平の林田良平宛ハガキ(香坡遺族のこと)、昭和17、1枚
他22点
(雑誌・書籍の部)絵葉書
50 柿衞文庫(秀品集B):柿衛文庫、昭和58、袋付8枚
柿衞賛麗画「三百年」・素龍筆「おくのほそ道」・漱石筆「蚊ばしらや」・碧梧桐筆「行水を」他・一茶筆「目出度さは」・許六筆「芭焦行脚像」・ 鬼貫筆「蕪村筆俳仙群会図」・鬼貫「によっほりと」
52 鬼貫賛春卜画巻(部分):伊丹市、昭和51、1枚
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 教育委員会 教育部 生涯学習推進室 歴史民俗資料館
〒563-0029
池田市五月丘1丁目10番12号
電話:072-751-3019
教育委員会教育部生涯学習推進室歴史民俗資料館へのご意見・お問い合わせ





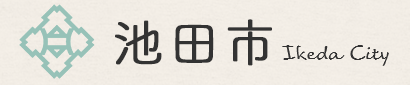

更新日:2021年02月01日