クビアカツヤカミキリについて
市内での発生情報
令和7年8月に池田市内においても特定外来生物「クビアカツヤカミキリ」による被害を確認しました。被害が確認された地域は下記の通りです。
| 年月 | 地域 |
| 令和7年8月 | 伏尾台1丁目、伏尾町、建石町 |
| 令和7年9月 | 畑2丁目、東山町 |
被害が確認された樹木については、公共地の場合は担当課と対策を実施しております。私有地の場合は土地の所有者へクビアカツヤカミキリが発生した旨をお伝えし、対策を依頼しております。
今後も池田市内の樹木のパトロールを継続していきます。
市民の皆様におかれましては、クビアカツヤカミキリによる被害を確認した場合は、環境政策課までご連絡いただくか、下記フォームより情報提供をお願いいたします。成虫を見つけた場合、可能であれば捕獲してその場で潰してください。
クビアカツヤカミキリとは
名称:クビアカツヤカミキリ
分類:コウチュウ目・カミキリムシ科
体長:2センチメートルから4センチメートル(成虫)
特徴:成虫は全体が黒く光沢がある。頭部の下(前胸の一部)が赤く、突起がある。繁殖能力が非常に高く、1匹のメスが生涯に300個から1,000個程度の産卵をするといわれる。
被害樹種:サクラ、ウメ、モモ、スモモなど、バラ科の樹木を幼虫が食害する
※クビアカツヤカミキリは平成30年1月に「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)」による特定外来生物に指定され、 飼養、保管、運搬、輸入、野外への放出等が原則禁止されています。
クビアカツヤカミキリの成虫
・6月から8月頃に活動する。越冬はしない。
・蛹から羽化してすぐに繁殖行動を行う。
・人の目につきやすい樹木の幹の2メートルまでの高さにいることが多い。
・香料の一種であるジャコウのような匂い(むせるような甘い匂い)を放つ。
・毒は無く、人に嚙みついたり危害を与えることはない。

写真提供:(地独)大阪府立環境農林水産総合研究所
クビアカツヤカミキリの幼虫
・樹皮の裂け目などに産卵された卵から孵化し、樹木内部に侵入する。
・幼虫の活動期は4月から10月頃まで。幼虫の状態で樹木内で約2年間を過ごし、蛹を経て6月から8月の間に成虫になる。
・樹木の内樹皮(木の中で養分を運ぶ部分)を好んで食べる。1匹が食害する範囲が広い。
・ほとんどは地表から2メートル程度の高さまでの幹や露出した根を食害するが、まれに高所の枝にも入ることがある。
・侵入した穴などから木くずとフンの混合物「フラス」を大量に排出する。
・樹木内の広範囲を移動するため、幼虫を発見して直接駆除することが非常に難しい。

クビアカツヤカミキリのフラス
・うどんのように、細長くつながった形状のものが多い。樹木内の樹液が少ないなどの理由でバラバラの場合もある。
・彫刻刀で削ったような少し丸みを帯びた木くずが混ざっている。
・樹木内部の空洞に詰まったフラスが押し出される形で樹木外に排出されるため、フラスを発見した時点で内部はかなり食害が進んでいる。
・樹木内にクビアカツヤカミキリの幼虫がいることを確認できる唯一の手段。
・フラスそのものには卵や幼虫はいないため、フラスから被害が広がることはない。

被害対策について
ご自宅の庭や畑など、ご自身が管理されている樹木でフラスなどの被害を確認した場合、ご自身で被害拡大防止のため対策を行ってください。
被害対策の詳細は、次の大阪府及び大阪府立環境農林水産総合研究所のWEBサイトをご確認ください。
≪大阪府≫
https://www.pref.osaka.lg.jp/o120030/midori/seibututayousei/kubiaka.html#tebikisho
≪大阪府立環境農林水産総合研究所≫
https://www.knsk-osaka.jp/nourin/news/2024032200014/





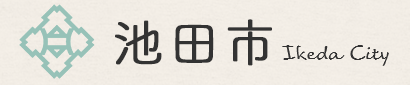

更新日:2025年08月21日