4.市民公益団体をとりまく環境整備のあり方
環境整備のあり方については、人、もの、資金、情報などの観点から検討を加え、別に市との協働のあり方について考察した。
1.環境整備のあり方
市民公益活動は、その社会的な目的、夢が求心力を求めて組織化され、具体化されていくのであるが、しかし、このようにしてできた組織も人間のライフサイクルに似て、自立化、活性化、サロン化、形骸化の道を歩む。そして、機能しなくなった団体は消え去り、また、その後に新しい「思い」が起こるという淘汰を繰り返す。そういう意味では、それぞれの段階に応じた環境整備や支援が求められるが、しかし、これらの現象は団体という組織体にとらわているために生じてくるものである。
環境整備のあり方については、市民公益活動団体が社会的に影響力を与えている活動の公益性や公共性に着目するとともに、「本来、市民活動、NPOの支援はNPOセクターによってなされるべきである」という一般原則を損なうことなく、言い換えれば、直接団体に干渉することがないよう、間接的、側面的に支援することを考えねばならない。
このような観点から、行政による支援には、活動の自発性(自主性)、取扱いの公平性(公正性)、支援手続きの公開性(透明性)を保証していくとともに、その活動の公益性を尊重し、さらには、支援が税でなされていることを十分認識して行わなければならない。今後、団体への支援は「自立支援」というよりも、むしろ、公益活動が活性化するよう、また、その活動意識を高める方向でなされることが重要と思われる。
(1) 人
各団体の課題で目につくのが「人」である。その主なものをあげると、「後継者不足」、「会員の固定化」、「会員の高齢化」、そして「特定者に責任が集中する」、「リーダー不足」などとなる。
そこには、身近に活動の機会がない、募集しても若い人を活かす場がない、仕事等のために活動に専念できないなどの理由があるが、これらの状況は、団体に新しい応募者がない限り、また、活動が会員(活動員)の年齢に応じて変化しない限り、その活動を維持できないことを示している。
しかし、既存の団体の多くがセミナー等を受けてグループ化されたことを考えると、人々をひきつける上で講座等の開催は引き続き重要であり、加えて、学校での授業等に公益活動を組込み、また、高校生、大学生にも積極的に参加をよびかけ、さらには、ボランティア休暇の普及に対応して勤労者を活かす場をつくることが必要となってくる。そのためには、団体自身も新たなプログラムを開発し、併せて、活動への参加を促すムードづくりと、このような人々を受け入れる態勢づくりが急がれる。
一方、若い活動者を育成するために、独自に、講座、研修会を持つ団体もあるが講師代等に苦慮しており、また、市の主催する研修会では、参加が役員の役割として捉えられ受講者が特定化してしまう傾向がある。これらを解消する方法として、地域で汗を流している活動者に講師を依頼し、互いにそのネットワークを広げていく、また、主催は団体、資金助成は行政、企業セクターといった共催による解決方法も考えられる。
いずれにせよ、目的や活動が異なる団体で一様にはいかないが、同一分野内においても横のつながりが少ない現状を踏まえ、これらの団体が一堂に集まる「催し」を行い、交流を通じて意識を高め合い、また、人材を発掘していく。お互いの経験を共有し、活動を活性化させるという視点も必要である。
将来的には、団体を組織的にマネジメントする力量を持つ人材と市民の参加などをコーディネートする人材の養成は不可欠となろう。また、リーダー不足についても、団体内で特定の責任者に事務、責任を集中させてしまう(任せきりになる)傾向があり、その負担ゆえにやり手がなくなっていくという現実がある。その裏には、顔見知りによる活動員の補充や団体発足時の「思い」へのこだわり、活動の惰性化、役を手放さない自己保身などが新しい活動員の「思い」、「やる気」を封じるといった実態もあるのだろう。しかし、それ以上に個々の活動員に使命や役割が与えられていないこと、全てを抱え込んでしまう日本的な責任感のあり方にかかるところが大きいと思われる。 組織によっては役員に過重な責任を負わしていることがあり、団体を分化させたり、小さな団体を多数つくることによって個々の負担を軽くし、また、それをネットワーク化することによって、小回りがきき、同時に、大きな事業も展開できる活動が可能となる。このように大きなリーダーよりも小さなリーダーの道もある。50人或いは100人に一人あるかどうかといわれる貴重な人材に、それに必要な研修等の場や他団体との交流の場を与え、じっくりと育て上げていく必要がある。
一方、活動を受ける側の問題として、なかなか心を開いてもらえないという状況がある。市民公益活動は、その対象者にお礼の言葉を求める活動でもなく、まして、ストレスを与えるものでもない。市民公益活動にあっては相手の人権を尊重するとともに、双方向の「心のふれあい」が必要であり、活動の原点が「楽しみながらする」ものなら、当然、相手にも「楽しみになる」ような活動方法が求められる。今後、行政、企業、団体が互いに持つ人的、物的ストックを共有化し団体自ら研鑚できるよう、また、活動について広く理解を得るよう社会に働きかけていく必要がある。
さらに、活動の需要と供給を調整したり、義務感にさいなまれている活動員をねぎらうコーディネーター(カウンセラー)的な人材の育成や活動に伴う専門的な技術、知識を提供する人材を確保し、活動の質を高めていくことも重要である。
(定年後の男性の社会参加)
これらと少し観点が異なるが、市内の公益活動の多くは女性で支えられている。しかし、夫の定年により、地域の一員として活躍してきた女性は、再び、家庭に縛られ、時には、ライフスタスイルの急変により、重いストレスを受け、活動に復帰できないこともある。長年、会社人間、企業戦士として働いてきた男性にとって、社会参加、特に、対等を旨とする地域活動には居場所も無く溶け込みにくいものがある。既に企業においては、定年前に社会参加の講座を持ち、社員を家庭、地域に戻す試みもある。しかし、日頃から、地域の具体的な活動を目で見て、理解させるよう女性がフォローしなければいつまでも会社人間のままでいかねない状況もある。
これらのことは、男性自らが意識を改革していかなければならないのだが、そのきっかけづくりのためには、地域の中に気の合った男同志が語り合える場や身近な活動の機会と心許せる仲間からの誘いが必要である。
(2) 活動資金
市内の市民公益活動団体の多くは、財政規模が年間30万円以下の上部組識や下部組織を持たない草の根団体で、しかも、地域の支援もなく、活動の無報酬性を唱えたボランティアグループとして発達してきた。しかし、今後、活動を継続し「思い」を遂げるためにも、また、利用者に継続的な活動を約束するためにも、活動員に交通費等の費用を弁償できるよう自主事業の拡大や有償活動も視野に入れておかなければならない。さらに、活動成果を地域に問う形で地域との連携を深め、今後、積極的にサポーターづくりをすることも必要となろう。
<1>補助金
市民公益活動は、本来、市民の「思い」でなされ、補助金に頼ることなくその活動が継続されるべきものであるが、現実には、補助金は団体にとって会費に次ぐ重要な資金源となっている。しかし、このような補助の中には、「組織維持のための補助」と思われる一律的で慣例的な補助があり、かえって不公平感を招いているものがある。今後、団体への補助は、活動の公益性、活動意欲、影響力などを考慮し、活動内容そのものに対してなされるべきである。ただし、団体に加入していない者とのバランスも考え、また、納税者の立場から、それが有効利用されたか否かが公正、中立、横並びに評価される仕組みも必要となろう。
また、これと観点は異なるが、補助金に代わるものとして、公共施設を収益事業や会員獲得事業に開放する方法があり、さらに、行政、企業、市民有志による寄付の受け皿として基金を設置し、そこから一定のルールのもとに市民公益活動に財政支援していく方法なども有効である。
<2>寄付
企業や市民から寄付を受けている団体は少ない。それは、社会貢献活動をする企業が増えたものの、まだ、寄付の相手方としてNPOの認知度は低く寄付の対象とは認められないこと、また、寄付をしても次の収益に結びつかないためだろう。営業利益の一部を寄付という形で引き出す以上は企業のメリットをも考慮し、さらに、企画書、事業計画書の提出や事業実施報告をするなど、団体自身も、社会的信用を得る形で対応すべきである。また、企業としても寄付に対する考え方やその対象分野などを予め知らせ、その企業姿勢を世に示すことも大切である。
これらのことは、市民に対しても言えることであり、その寄付が有効に活かされたことを寄付者に報告するなど運営の透明性を自ら確保していかなくてはならない。
また、この外に、企業が持っている設備、備品、商品の提供や金融機関によるNPO法人への低利貸付など、その事業に応じた幅広い支援が考えられる。このような企業による社会貢献的な活動には、会社と地域社会との共生という外に、会社を構成するものもまた「人」であり、会社の利益だけではなく、広く社会のために業を営んでいるのだと、また、消費者という人によっても支えられているのだという視点が必要かもしれない。
(3) 場所
<1>拠点整備
団体の事務的な作業場所として既存の公共施設の使用が最も多く、次いで会員宅となっている。しかし、使いやすい場所に人と人のネットワーク化を可能にする「ふれあい」の場が必要である。活動する側と活動を受ける側をコーディネートする場、各団体が情報交換をする場、市民と活動者が相談をする場、電話、配送物の取り次ぎをする場、団体を支援する場としての総合的な窓口が必要であり、機能を集中させることによって統制するのではなく、情報や人を流れやすくする体制を整える必要がある。
通常、これらの活動は財団を含む中間支援組織が行うことがふさわしいが、本市にはそこまで実力の備えた団体等は見当たらず、その設立、インフラの整備や運用は、行政や企業の支援無しには不可能と思われる。
このように拠点とは、施設と活動を支える者の総体をいうのであるが、その整備は、単に建物にとどまらず人を介して人材育成、調査研究機能、NPO評価機能などを備える、さらに、ネットワーク支援機能としてボランティアだけでなく民生委員児童委員等にも幅広く使ってもらえるようなものであることが望まれる。当然、これらの機能を果たすためには、コピー等印刷関連機器、ファックス、パソコン等通信機器など総合事務所としての諸設備が必要とされる。
既に、他市のNPOセンターの中には、行政の規制に縛られず、各団体が集まり自ら組織、運営しているところもある。申込み等の事務手続きの簡略化、団体の話し合いによる独占利用、時間帯を定めないフレキシブルな利用、申込み重複時の他施設斡旋などの外に、活動者にとっては単に会議室としてではなく、作業をする場、昼食のとれる場など常識内の自由利用ができる市民の目から見た規制の少ない運用が求められる。
<2>活動場所
一方、団体等の活動、催しもの、講習の場として、学校等の休日開放、既存施設の整理にともなう余剰施設の活用などが考えられる。特に、家賃に困っているNPO法人等の事務所や物品の置き場所として利用の余地がある。
現在のところ管理費を自己負担して活動する団体等は見当たらないが、一つの地域で団体が集まり試験的に実施することも考えられる。しかし、これらの施設の使用については応分の危険負担が求められ、使う側・貸す側双方に事故に備えた保険加入等が必要である。また、市内には、食事づくりをしながら多人数で集える山の家のような室内施設が少なく、また、野外で行事をするについても、トイレなど設置されるべき設備が不足しているところもある。既存施設の整備も併せて考慮すべきであろう。
(4) 情報
従来の市民公益活動団体の多くは、行政及び社会福祉法人などのつながりの中で発展してきたため、その縦割り組織の影響を受け、異分野間の交流は少ない状況にある。それゆえ、主な情報源は、関係組織、市、そして関係者からの口コミとなっている。
そこでは、活動者の募集が口コミでなされ、また、活動者の知識、技術の向上が講演会への参加や独自の研修会を通じて行われており、人そのものを媒体に情報ネットワークが形成されている様子がうかがえる。このような実態を踏まえると、団体内の連絡はもちろん、横の連絡や異分野間の連絡に必要な口コミの場として、情報拠点の整備は急務である。
今後、活動を幅広く市民に理解してもらうためにも、広報誌の利用、情報誌の配布、公共施設での掲示板の相互利用、ホームページの開設等多様な広報手段・媒体が求められる。さらに、これらの発信に関わっていくとともに、市民に必要な団体の情報を一元的に登録管理し、絶えず更新するなど情報整理をする仕組みも必要となる。
(5) 制度(組織)
行政は、ピラミッド型の効率的な内部機構を持ち、また、セクター全体もピラミッド型に構成されている。かたや、企業にも同様の内部機構があり、セクター全体が多重的、多層的に構成され多様なサービスを提供している。
一方、NPOセクターには専従スタッフ(職員)を持たない団体が多い。それゆえ、組織的には活動員がそれぞれ対等な関係で結ばれており、指示系統にあいまいさがあるものの、逆に、個性を殺すことなく、多元的で多様な価値観のもとに活動をしている。
これらの特質は、NPOセクター内の制度、組織を検討する際、重要なものとなる。つまり、セクター全体をピラミッド型ですみわけをすると多様な市民の活動を一元的な価値観で集約したり、団体間の競争をなくし全体として不活性な状況をつくりだすことがある。既に用を成さなくなった団体がいつまでも生き残り、新たな「思い」を持った団体の結成を駆逐してしまう。
NPOセクターが活性化するためには、それぞれの「思い」を持つ団体が多重的、多層的に存在し、競争することによってよりよいサービスが社会に提供される仕組みが要る。お互いの価値観を認め合いながらもより優れたサービスが残っていくような、NPOセクター自らの手による組織づくりが原則である。
さて、これらのことを考慮しながら活動を促進するため、制度化、組織化が急がれる仕組みがある。これらの内、最も重要なものとして、公益活動の需要と供給を取り持つ仕組みがある。常時、相談窓口的なものがあり、活動希望者を受け入れる団体を登録し、リアルタイムで情報を替えていく。また、団体への活動要請が常に切迫した状況のもとに来るため、それに「迅速」に対応していく仕組みも必要となってくる。さらに、専門的な知識や技術を有する人材を拠点にストック(登録)する制度も活動の活性化、専門化には欠かせない。これらの機能は、市内だけにとどまらず各団体の活動領域に応じて広域的に調整される必要がある。
一方、市民公益活動は、企業にとって直接メリットをもたらすものではないが、社会貢献活動を行う企業、団体と関わりのある公益法人、市、そして団体などとが独立した組織を設け、交流を図る。あるいは、広域的な連携を確保し、情報を伝え合っていくといったセクター全体のネットワーク化の中で企業の連携、協力のあり方が模索できる。
さらに、市についても社会に役立ちたいと思っている人々を受け入れる窓口を設け、その仕事に熟知している部門が企画した協働のプログラムを推進していく。例え参加が少なくても各分野で回を重ねることによってその経験がいかされていくと思われる。
2.市との協働のあり方
近年、パートナーシップの日本語訳として「協働」という言葉が使われる。これは、共通の目的に向かって行動する組織間の連携という意味合いで、共通の利益や関心を持った団体、組織等がそれぞれ持っている時間や能力を相互に活かすという協力関係でもある。
本来、市民活動は独立した「意志」と「責任」を担える組織となってはじめて社会的に認知され、また、受け入れられていくものと考えられる。このことは、公益的な活動を行う団体にも言えるのであるが、その活動が行政に近いところで行われることも多く、その「思い」はしばしば行政の施策と重複し、渾然一体となる。しかし、行動原理や質の異なる活動であることをお互い理解すれば、協働に際しては、市の財政改革の一環として、また、行政の下請けとして、さらに「動員」要員として、合意なしに行政のシステムに組み入れられるものではない。
(1)協働の精神
市民公益活動は自発的なもので、市との協働についても、その活動はあくまで個人によってなされるという視点が必要である。そして、その内容も義務として拘束するのではなく、楽しみながら続けられる方法が求められる。単に、無償の労働力だということで本来市のやるべき事を転化しないように留意すべきであり、それについての職員の意識改革も求められる。
また、市は、協働を強要する形で団体に干渉していくのではなく、協働に関わる情報を積極的に開示し、予め団体を募る、団体も主体性を持って市の協働を引き出す姿勢が大切である。
このように、目的を一にする協働は、双方が独立した対等な立場のもと、相互に理解し合うことによって成るものであり、その活動の成果は、NPOセクターの行動原理を踏まえた上で評価されなければならない。
(2)協働の範囲
市の業務を丸投げにするのではなく、本来、市が専門的に行うべき業務と団体に委ねられる業務の別があり、その業務を熟知している関係部課が協働のプログラムを開発していくことが大切である。場合によっては、団体と業者が取り扱う業務のすみわけも必要となるが、市の財政状況等からみて業者発注が不可能なら、団体が出来る技術の範囲で協働すれば、そこには自ずと質的、量的に一定のボーダーラインが生じ、業者を圧迫することにはならない。今後、実績を重ねることによって協働の範囲が明確化され、歩み寄ることができる。
(3)機会、場の提供
ボランティア活動をはじめとして公益活動をしたいと思っている人は多いが、気軽に参加する機会がつかめない。市が、公園などの施設管理を募集すれば、男性の活動者を掘り起こすよい機会となる。初めはその活動が本人の「思い」と異なるものであっても、月に一度、気軽に参加できる機会を設けることによって次につながる。市民の協力したいという気持ちを汲み上げる意味で、市も、公共施設を積極的に開放していくべきである。
ただ、これらの活動も個人レベルでは気恥ずかしさを覚えることもあり、作業をグループ化したり、統一された帽子等により市の協働者であることが認知されるような配慮がいる。
また、市が団体と協働するためには、市がテーマを提供して新たな団体の結成を促す方法と既存の団体に呼びかける方法があるが、自主性を損なわないよう、特に、後者については「動員」にならないよう留意が必要である。
(4)責任の所在
市が団体と協働するに際しては、これらの活動が制度として抱え込まれないよう、活動するものの「主体性」、「自律性」が尊重されなければならない。特に、参加回数が求められる形で協働がなされると、個人的なレベルで「楽しみ」が 「重荷」、「辛さ」に変わってしまうことがある。ボランタリーな活動は、常時、駐在して活動してもらえる保証もなく、ある時期、突然、やめるということも起き得る。言い換えれば、市の最低保証のもとに団体との協働が成り立ち、最終的に、市は管理者としての責任が必要となることもある。当然、団体も、約束という社会ルールは守らなくてはならないが、活動員の管理上、特に必要が無いなら契約書など個人的に精神的な負担となる手続きは避けたいところである。むしろ当分の間は、市が最低すべき業務の上に、多様な付加価値を付ける活動、その効果を高める活動と捉まえる方が両者のリスクは少ない。
一方、活動員個人も活動場所での対応にとまどったり、義務感にさいなまれたり、また、家庭との狭間で悩みなどが生じる。これらについても、協働する市、団体双方に「ねぎらい」や「相談の場」が確保されていることが望まれる。
(5)事業委託
現在、市業務の見直しの一環として民間企業への委託が進められているが、NPO法人及びそれに近い組織的な団体への委託はほとんど進んでいない。
NPO法人等にとっては、これら行政の目の届きにくい部分でフォローをするという役割もあるが、市としても、委託したい分野、将来、委託を進めたい分野を明確にし、その上で地域密着型の施策が成せるなら競争力の弱いNPO法人等のために随意契約による協働を打ち出すべきである。
ただ、起こり得る究極のことがらや将来予測できないことを議論すると、やろうとするよりもそれに反対する意見が必ず勝ってしまう。枝葉の問題でなく、大きな問題から一つずつ掘り下げていく市やNPO法人等の姿勢が大切である。特に、業務委託については、それを受けるNP0法人等にも市民サービスを低下させないという責任の一端を担っているのだという責務がある。
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 市民活動部 コミュニティ推進課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所7階
電話:072-754-6641
市民活動部コミュニティ推進課へのご意見・お問い合わせ





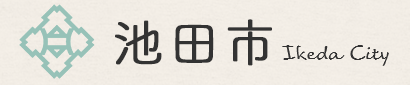

更新日:2021年02月01日