浸水対策事業の取り組みについて
近年、気候変動等による豪雨の増加により、水害が頻発化・激甚化しています。
池田市の下水道事業では、街を水害から守る浸水対策に取り組んでいます。
雨で街が浸水するしくみ
通常、田畑や森林等がある場所では、雨水のほとんどが地面にしみこんで時間をかけて川に流れ込むため、下水道へ流入する雨水は少なくなり、浸水を防ぎます。
一方、都市化が進んで田畑や森林等が少なくなると、地面の多くがアスファルトなどに覆われ、雨水はしみこむことができません。側溝や下水道を通って、川や下水処理場に入っていきます。短時間に強い雨が降ると、川や下水道で排出する能力を超えて、雨水があふれだし、街が浸水します。

(イメージ)
浸水対策における下水道の役割

下水道事業で浸水対策を行った城南3丁目付近

整備前

整備後(現在)
下水道で行っている浸水対策事業
八王寺川バイパス管
国道176号付近の八王寺川、荒堀川の水位が一定以上となると、八王寺川の地下7~10mに造られたバイパス管を通って夫婦池に雨水を一時的に貯留する施設が令和4年度に完成予定です。他にも、八王寺川雨水増補幹線・石橋第1増補幹線・石橋第2増補幹線といった施設があり、浸水対策の役割を果たしています。

八王寺川雨水バイパス管の写真とイメージ
池田市下水処理場の浸水対策設備
雨が降ったとき、下水処理場にも処理区域全体から雨水が流れてきます。流れてきた雨水は雨水ポンプを使って猪名川へ排水します。
豪雨が増加している中、下水処理場にある雨水ポンプも浸水対策の一つとして活躍しています。

池田市下水処理場にある雨水ポンプ
雨水を貯めて浸水を防ぐ雨水貯留施設
大雨が降ると、土地の低い場所では今ある下水道管では雨水を流しきれず、道路にあふれてたまってしまうことがあります。
雨水貯留施設は、下水道管で流しきれない雨水を一時的に取り込むことにより、浸水被害を軽減させる下水道施設です。現在、令和5年度の完成をめざして、城南~神田地区の浸水被害を軽減させることを目的とした雨水貯留施設の事業を進めています。

雨水貯留施設のトンネルを掘る機械

雨水貯留施設のしくみ(イメージ)
この記事に関するお問い合わせ先
- 皆様のご意見をおきかせください。
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。






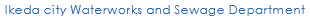
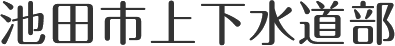

更新日:2025年02月17日