西国街道-京と西国を結ぶ主要道-
西国街道は京と西国を結ぶ主要道として位置づけられていました。かつては外国の使節が太宰府から京へ向かう際や参勤交代の際に通った主要幹線道でもありました。
かつて多くの人々が往来した主要道に思いを巡らせながら歩いてみてはいかがでしょうか。
モデル散策コース
今井橋東詰 -(0.6km)- 弁財天社 -(0.4km)- 旧石橋村の高札場跡(能勢街道との交差地)-(0.6km)- 亀之森住吉神社 -(0.3km)- 十二神社
西国街道周辺の文化財
能勢街道との交差
ここは大阪からきた能勢街道と京都からくる西国街道が交差する地点です。
江戸時代には、法令などを記した高札が掲げられた場所でもありました。
現在、この場所には道標2基と「石橋村」についての解説看板があります。2基の道標のうち1基は平成22年に設置したものです。もう1基は江戸時代に設けられたことがわかっています。
江戸時代に設けられた道標は各面に行き先とその方向が刻まれています。ただし、北面には道標を設けた施主名が行き先とその方向の下に刻まれていますが、現在は半分ほど地面に埋もれています。
また、西面に関しては線路側にありますので観察する際は注意してください。

東面
「すぐ西宮 右妙見」

北面
「左大阪 右西宮」

南面
「天保二卯九月」
西国街道周辺の社寺

順正寺

受楽寺
江戸時代には、順正寺・受楽寺ともにこの付近に高札場があったとされます。

十二神社
境内には防空壕が残っています。

亀之森住吉神社
神社には大阪府内で最も古い文化3年(1806)に奉納された算額(市重文)があります。
西国街道周辺の埋蔵文化財
宮の前遺跡
宮の前遺跡(豊中市は蛍池北遺跡と呼称)は現在の住吉1・2丁目、石橋4丁目から豊中市蛍池北町の範囲にあり、猪名川東岸の弥生社会を知るうえで重要な遺跡のひとつです。昭和43年(1968)に中国自動車道建設に伴い本格的な調査が行われ、弥生時代中期の竪穴建物跡や方形周溝墓が多数検出されました。

石包丁出土状況(第11次調査〈1987年〉)

竪穴建物跡(第11次調査〈1987年〉)

溝跡(第11次調査〈1987年〉)
溝からは多量の土器が出土した。

実測風景(第14次調査〈1988年〉)

発掘風景(第26次調査〈1991年〉)
十二神社境内防空壕跡
コンクリート製で昭和18年(1943)に周辺住民により造られ、30人程度が避難できる空間があったようですが、現在は安全面を考慮し内部を埋めています。
池田市に本格的に防空壕が造られるのは昭和20年(1945)に入ってからです。地域住民の避難場所として大阪府からの指示を受け、池田市域には人口が密集している旧池田町・旧北豊島村を中心に町会ごとに造られたようです。この際用いられた資材は大阪の疎開家屋の廃材でした。
このように十二神社境内の防空壕は他のものよりも築造時期が早く、池田に住む人々の戦争に対する認識を考えるうえで重要な遺跡です。

『広報いけだ』平成15年12月号から平成16年5月号で連載した内容を編集し新しくしたものです。西国街道沿いにある文化財についてより詳しく知りたい方はぜひご覧ください。また、街道のコースを地図や現地写真を交えて紹介しておりますので、ウォーキングのお供にいかがでしょうか。
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 教育委員会 教育部 生涯学習推進室 社会教育課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所5階
電話:
(社会教育)072-754-6295
(スポーツ)072-754-6480
(文化財)072-754-6674
教育委員会教育部生涯学習推進室社会教育課へのご意見・お問い合わせ
- 皆様のご意見をおきかせください。
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。





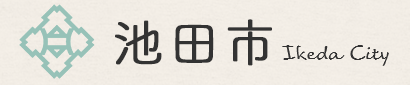


更新日:2024年11月18日