中学校部活動の地域移行について
(令和8年2月)
1月に実施しました中学校の新入学説明会において、部活動の終了時期等に関する説明を行いました。説明に使用した動画を掲載いたします。(学校名をクリックするとYou Tubeにつながります)
池田中学校はこちら
渋谷中学校はこちら
北豊島中学校はこちら
石橋中学校はこちら
ほそごう学園はこちら
(令和7年12月1日)
地域クラブの充実化に向けた財源確保に向けて、12月よりふるさと納税を活用したクラウドファンディングを実施します。
詳しくは下記HPをご覧ください。
部活動から地域クラブへ【池田の文化・スポーツを未来へつなぐ】プロジェクト(クラウドファンディング)
中学校部活動について
部活動について、クラスの枠組みを超えた生徒同士の交流やチームワークや忍耐力の涵養、体力向上などに大きな役割を果たしてきました。一方で急速に少子化が進み、設置部活動数の減少や単独では試合に出られない部活動もあるなど、学校単位での維持が難しくなってきています。加えて、全国的に教員の多忙な働き方が注目される中、本市の教員についてもその長時間労働は顕著であるとともに、教員採用試験の志願者数が減少しているなど、教員不足の深刻化も予想されます。
このような現状を踏まえ、本市では「部活動地域移行推進計画」を策定し、2028年度(令和10年度)中に部活動を終了し、生徒が地域の中で文化・スポーツ活動をする「地域クラブ」を開始します。
様々に課題はございますが、今後も生徒が主体的に選択肢、多様な活動に参加できる機会を保障できるように取り組んで参ります。ご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。
地域移行に関するリーフレット (PDFファイル: 433.2KB)
各小学校での説明資料はこちら (PDFファイル: 795.7KB)
部活動地域移行推進計画 (PDFファイル: 904.6KB)
現在活動している地域クラブ活動はこちら!
2025年10月より新たな実施種目が増えました!詳細については、スポーツ系・文化系のページよりそれぞれご確認ください。
部活動の地域移行に関する質問はこちら↓
想定質問一覧(ご覧になりたい質問をクリックいただくと該当箇所へ遷移します)
| なぜ部活動を地域移行する必要があるのですか? |
| なぜ平日も含めて地域移行するのですか? |
| なぜ2028年度(令和10年度)中に地域移行するのですか? |
| 地域移行計画について、どのような過程で議論され、決定しましたか。 |
| 移行時期の生徒は部活動と「地域クラブ」をどのように選択すれば良いですか? |
| 移行時期の子どもが困らないよう配慮してもらえるのですか? |
なぜ部活動を地域移行する必要があるのですか?
部活動については、生徒たちが異学年やクラス以外の生徒と交流する中で、チームワークや忍耐力、体力や技能の向上など、大きな役割を果たしてきました。一方で、少子化が進む中で、部活動の廃部や単独では試合に出られない部活動があるなど学校単位での活動の維持が難しくなっています。また価値観が多様化する中で、部活動に求められるものも多様化しており、教員間・生徒間でも「部活動」に対する考えが異なってきております。加えて全国的に教員の多忙な働き方が注目されるなか、本市の教員についてもその長時間労働は顕著であるとともに、教員採用試験の志願者数が減少するなど教員不足の深刻化が予想され、専門性や意思に関わらず教員が顧問を担う仕組みは限界に近づいています。
このような現状を踏まえ、本市では2028年度(令和10年度)中に部活動を終了し、生徒が地域の中で文化・スポーツ活動をする「地域クラブ」を開始します。
様々な課題はありますが、今後も生徒が主体的に選択し、多様な活動に参加できる機会を保障できるよう取り組んでまいりますので、ご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。
なぜ平日も含めて地域移行するのですか?
部活動については、その制度自体に課題が多く、休日のみの移行は少子化への対応や教員の働き方に対する根本の解決策にはならないと考えています。生徒への質の高い文化・スポーツ活動を維持していくためにも本市では平日・休日ともに地域移行することとしています。
なぜ2028年度(令和10年度)中に地域移行するのですか?
学校における働き方改革等も踏まえて、部活動を学校単位から地域単位の取組としていく方向性を2019年(令和元年)に国が示しており、2022年には「2023年度から2025年度までの3年間を改革推進期間として、地域の実情に応じて可能な限り早期の実現を目指す」というガイドラインが公表されました。また、2026年度(令和8年度)以降についても、平日も含めた地域展開を目指していく方針が議論されています。
本市では、移行先となる受け皿の確保や地域移行に対する共通理解の定着等も踏まえ2028年度(令和10年度)中の地域移行を目指してまいります。
地域移行計画について、どのような過程で議論され、決定しましたか。
地域移行については、令和5年度より、教育委員会とそれぞれの中学校長、地域クラブを実施されている方と議論を進めてきました。令和6年度からはPTAの代表者なども加わって、「部活動地域移行協議会」を設置し、地域移行の目指すべき姿やそのスケジュールを議論し、協議会での意見を踏まえ、教育委員会で「地域移行計画」を策定し、決定いたしました。
移行時期の生徒は部活動と「地域クラブ」をどのように選択すれば良いですか?
2028年度(令和10年度中)に現在の小学校5年生が中学校2年時、現在の小学校4年生が中学校1年時に完全に移行します。現在も地域クラブについては様々な種目で実施されており、令和10年度まで待たずとも、興味がある活動があれば地域クラブに参加することは可能です。地域クラブの中には小学生向けのクラブ運営を行っているチームもあり、中学校に進学後、引き続き参加することも可能です。もちろん部活動に参加することも可能です。
移行時期の子どもが困らないよう配慮してもらえるのですか?
年度途中で部活動が終了する学年については、同じ競技や興味がある種目が継続できるように情報提供を行うとともに、スムーズに移行ができるよう実施団体や学校と協議してまいります。また地域クラブの実施種目については、2028年度の完全地域移行に向けて、その種類を増やしていきたいと考えています。
現在の平日の部活動は何時から何時まで活動しているのですか?
学校ごとに若干異なりますが、授業終了後15時半ごろから活動を開始し、17時~17時半には完全下校いたします。平日については1時間~1時間半ほどの活動時間となります。
部活動はどれぐらいの頻度で活動しているのですか?
スポーツ庁・文化庁は週当たり2日以上の休養日を設けるガイドラインを示しています。本市もガイドラインを策定しており、部活動の活動頻度は週当たり最大5日(平日4日、休日は土日のどちらか)としています。また、1日の活動時間は、平日は2時間程度まで、休日は3時間程度までとしています。
顧問の先生は経験者として専門的な指導をしているのではないのですか?
経験のある種目を指導している教員もいる一方で、5割の教員は経験のない種目を指導しています。また教員の異動等もあり、翌年度も同じ種目を受け持てるわけではなく、赴任校の状況等で、受け持ちの部活数は変動します。
部活動の設置状況はどのような状況ですか?
学校によって部の数や種目にバラつきがあり、比較的競技人口が多い種目(例:サッカー、バスケットボール等)であっても進学する予定の中学校に部活動があるかどうかは分からない状況です。また仮に進学予定の中学校に部活動があったとしても、生徒不足で満足に試合ができない部活動や、顧問の教員が未経験の場合もあり、その内容の充実度にもバラつきがあるのが実態です。今後、少子化が進むことで、休部や廃部、単独で試合に出場できない学校が増えることが予想されであり、学校単位での部活動の維持が困難な状況になっています。
子どものニーズが変化しているとは、どういうことですか?
令和6年度に高学年に、「中学生になったら取り組みたい文化・スポーツ活動」をアンケートしたところ、上位の回答にダンスや硬式テニス、英語、パソコン(プログラミング)など部活動にはない種目があげられております。また活動頻度についても、平日であれば「2回」、休日であれば「休日は活動したくない」が最も多い回答でした。このような状況を踏まえると実施内容はもとより、活動の頻度についても、生徒のニーズが変化し、現状の部活動とは合致していないことがうかがえます。
部活動は内申書に影響があると聞いたことがありますが実際はどうでしょうか。また地域移行後はどうなりますか。
部活動に入部している、していない等による内申書に影響はありません。地域移行後も変わりはありません。
部活動が地域に移行された後、学校では空いた時間をどのように過ごすのですか。子どもたちにはどのように還元されますか。
これまで部活動終了後に行っていた教材研究を充実させたり、教員の校内研修や研究授業等を実施したりします。教員の資質向上を図り、日常の授業改善に努めます。
部活動は、教員と生徒の信頼関係を築く場となっていたと思いますが、部活動が移行された後、どのように教員との関係を構築していきますか。
最も多くの時間を過ごす授業や休み時間、昼食の時間等、教員と生徒の関係を築く時間を大切にしていきます。
部活動は、異学年の人間関係を学べる場でもあったかと思いますが、移行後は学校にそのような場はあるのでしょうか。
異学年の人間関係を学べる場として、委員会活動や生徒会活動、学校行事における縦割り活動等があります。
2028年度までは部活動が継続するのでしょうか。
現在も人数が不足している活動があり、2028年度まですべての部活動が継続できるわけではありません。ただし、「地域クラブ」も充実化してきており、地域のクラブとは十分連携を図りたいと考えています。
今ある中学校部活動を「地域クラブ」が担うことになりますか?
現在の部活動が、そのままの形で「地域クラブ」活動へ移行するわけではありません。これまでの部活動種目や頻度にとらわれず、新たな文化・スポーツ環境を構築し、子どもたち自身が目指したい姿、かなえたい目標を実現できる活動が選べるように進めてまいります。
「地域クラブ」は複数の中学校部活動を集約して実施するものですか?
中学校が活動主体である「部活動」は令和10年度内に完全に地域移行となるため、「地域クラブ」は部活動とは全く別の活動になります。部活動は学校教育活動ですが、地域クラブは学校教育とは異なる社会教育活動となります。
「地域クラブ」は部活動の意義を継承していくのですか?
部活動については、生徒たちが異学年やクラス以外の生徒と交流する中で、チームワークや忍耐力、体力や技能の向上など、大きな役割を果たしてきました。一方、地域クラブについても、担い手こそ異なりますが、生徒同士が切磋琢磨し、自己の研鑽や、チームワーク、体力の向上・技術の習得などを体得することができます。部活動が果たしてきた役割も継承しながら、地域に根差して生徒たちの成長を見守って参ります。
「地域クラブ」は誰が実施するのですか?
スポーツ・文化芸術団体、民間企業、NPOなど、地域で活動されている団体を想定しています。保護者の方が指導者として加わっていただいているクラブもあります。また、希望する教員については兼職兼業の許可を受けて参加することも可能です。
「地域クラブ」はいつ活動するのですか?
中学校施設を利用する場合は、令和10年度までは部活動も並行して行われていますので、平日・休日ともに18時から21時の間で活動しています。公共施設・民間施設を活用する場合はそれぞれの地域クラブが活動しやすい時間帯を設定しております。
「地域クラブ」の参加には月会費が必要になるのですか?
スタッフの報酬や保険にかかる経費が生じるため、各活動団体が継続的に活動していくためには、保護者の方に月会費や年会費として一定の金額をご負担いただく必要があると考えています。具体的な金額については、活動回数、活動人数、指導者の数などに応じて、各活動団体が設定することになります。
「地域クラブ」中の事故は誰が対応するのですか?
「地域クラブ」の活動主体は各活動団体となるため、事故等が生じた場合は(学校施設・設備に不備等があった場合を除いて)基本的には各活動団体が責任を負うことになります。そのため、万が一の事故に備えて、参加する生徒をはじめスタッフにも原則として保険加入していただきます。
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 教育委員会 教育部 生涯学習推進室 社会教育課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所5階
電話:
(社会教育)072-754-6295
(スポーツ)072-754-6480
(文化財)072-754-6674
教育委員会教育部生涯学習推進室社会教育課へのご意見・お問い合わせ
- 皆様のご意見をおきかせください。
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。





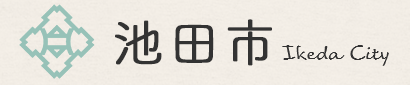

更新日:2026年02月01日